本文
みなみのわのむかしばなし各巻紹介
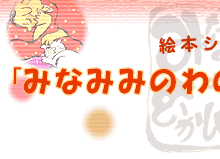
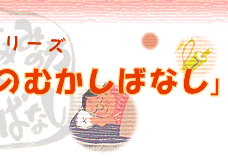
 「かまどぶ」
「かまどぶ」
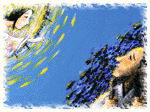
昔、鎮守の森の小高い丘の上に、天狗社と呼ばれるお社があった。
そのお社の近くには小さなお寺があり、下のほうに「かまどぶ」と言われる大きな沼があった。
今ではわずかにその名残をとどめるだけになったこのかまどぶには、都から島流しにされた若いお坊さんと、そのお坊さんを慕って長い一人旅をしてきた美しいお姫様の、悲しい悲しい物語が語り継がれている。
![]()
![]()
![]()
 「来る身塔婆」
「来る身塔婆」
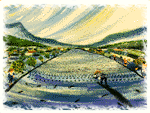
広い耕地を持った地主に年季奉公をしている娘がいた。働き者で気立ての良いこの娘はみんなから大変かわいがられていた。卯の花の咲く頃、娘に父親が亡くなったという知らせが届いた。一人残された母を思い、帰りたいと願い出た娘に、地主はこう言った。
「日の出から日の入りまでにあのでけぇ田んぼの田植えをし終えたら・・・」地主との約束を果たすため、娘は朝早くから田植えを始めるが・・・
![]()
![]()
![]()
 「お四国さま」
「お四国さま」

幼い時両親を相次いで亡くした嘉吉は、人の命のはかなさやこの世に生きることの意味を心に問い続けていた。ある晩、弘法大師の夢を見、大師の姿に今まで味わったことのない安らぎを覚えた嘉吉は、7年の歳月をかけ、海を渡り山を上り、難所をいくつも越え四国八十八か所霊場めぐりをした。「故郷に霊場を造り、多くの人と喜びを分かちあいたい」嘉吉の一途な思いが、新四国霊場を誕生させた。
![]()
![]()
![]()
 「不死清水」(しんずらしみず)
「不死清水」(しんずらしみず)
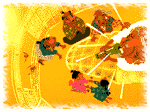
昔ある里に人々の面倒を大変よく見る長者様がいた。長旅に出るたび街道にこんこんと湧き出る清水を飲むことを何よりの楽しみとしていた。幾年かが過ぎ、重い病についた長者様は、「あの水が飲みたい」と言う。水を汲みに出た使いの者はやっとの思いでたどり着いた清水で、「主人はもう死んずら・・・でもせめて一口だけでも・・・」と帰り道を無我夢中で急ぐ・・・。
![]()
![]()
![]()
 「オトボー池」
「オトボー池」
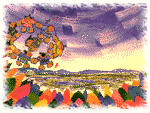
昔、雑草の生い茂る村境の湿地帯に「音羽の池」と呼ばれる大きな池があった。その池に伝わるお話。この村に住むたいそう釣り好きな男が畑仕事をしていると、旅の僧が通りがかり、「殺生もほどほどに、特に大きななまずを釣ることはお止めなさい」と声を掛けた。僧の言葉が気になりながらも、釣りに出かけた男は、いつまで経っても帰ってはこなかった。以来、池からはなぜか「オトボーさらば」という怪しげな声が・・・。
![]()
![]()
![]()
 「長者の井」
「長者の井」
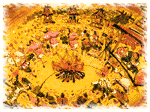
村の一番南に位置する沢尻村は、ある時期、村の一番北にある久保村の名が付いて「久保沢尻村」と呼ばれていた。その村名にまつわるこんなお話。今は戸谷川の底になっているが、沢尻村には「長者の井」と呼ばれる井戸があり、宮島式部という長者が住んでいた。豊年祭りがにぎやかに行われたある夜、何の前ぶれもなく村には火の手が上がり、盗賊の一団に襲われた・・・。
![]()
![]()
![]()
 「子安観音・お子安様」
「子安観音・お子安様」

昔、お産は女性にとって命がけの大仕事であり、各地区に「取り上げ婆さ」と言われるお産婆さんが必ず一人や二人はいたものだった。子安観音は、煙草が大好きで、「ホイ、キタ」と赤子を取り上げてくれる、大変腕のよい久保のお産婆さんの話。
お子安様は難産に苦しんだ折、夢枕に立ち、安産を授けてくれた観音様のご恩を一生忘れずに、村中のお産のお手伝いをした田畑のお産婆さんの話である。
![]()
![]()
![]()
 「大泉川の水」
「大泉川の水」
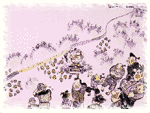
むかしむかし、長い日照りが続いたある年の夏、大泉の川の水はすっかりかれてしまった。困った村人たちは、神様に水を流してくれるようにお願いしたが、上流も下流も水が流れたのに、どういうわけか大泉だけは水が流れなかった。「神様はおれたちの力を試しているのかも知れねえぞ」と、ついに村人たちは自分たちで水を引いてくることを決意した。幸せな地域づくりには何が必要かを教えてくれるお話である。
![]()
![]()
![]()
 「上人塚・目の神様・霊松一本木」
「上人塚・目の神様・霊松一本木」
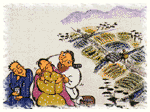
上人塚は、むかし天災や凶作、はやり病が村に広がったとき、通りすがりの村のため一心に祈りを捧げ、自らの命を落としながら村に笑顔を取り戻してくれた旅の僧のお話。
目の神様は、両目を患うお婆さんが、日ごろの感謝の気持ちから、川へ丈夫な橋を掛けたことからはじまるお話。
霊松一本木は、樹齢500年以上、高さ30メートル、廻り5メートルもあり、天然記念物にも指定されたという存在感のある松のお話。
![]()
![]()
![]()
 「薬師堂の焼け仏・御射山様」
「薬師堂の焼け仏・御射山様」
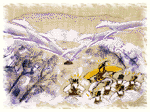
昔、村の子供たちが天竜川で遊んでいて黒焦げの傷ついた仏様を見つけ、村まで運んだ。大人たちは「こんなもの」とは思わず、「ご縁があってここまで来なさったんだ」と、小さなお堂を建てて手厚く祭ったその仏様にまつわる話。
春日街道を神子柴に入ると道の西側に、大きな落葉松が二本立っていて、その下に「御射山社」の碑がある。その碑と「やまとたける」にまつわるお話が御射山様である。






