本文
「かまどぶ」のあとがき
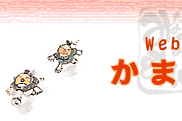
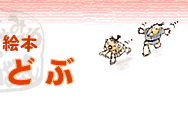
![]()
昭和30年代、上伊那誌編纂資料のため採集された伝説を載せている冊子には「釜どぶ」と記され、南箕輪村誌「説話・伝説」には、どぶの近くで焼き物に適する土が出ていることから、「窯(かま)」に関係があったのではないかとの考えから「窯どぶ」としました。
その後、「かま」(「渓流の小さな淵」を意味する)という字(あざ=土地の一区画ごとにつけられている名)に続いて「かま田」という字があり、その字の中に「かまどぶ」があることを確かめました。
土地の特徴をとらえて使われたこの地名の「かま」こそ、この「どぶ」につけられた正しい呼び名だと判断して、「かまどぶ」と表記しました。
坊さんの死の場面が、「村誌」とこの絵本で違う表現になっているのは、「かま」の解釈の違いからです。
「島流し」というのは、古代から明治初めまで続いていた「流刑(るけい)」(居住地から所定の国へ追放される刑)のことです。この刑に、「遠流(おんる)」「中流(ちゅうる)」「近流(ごんる)」があり、信濃国は、「中流(ちゅうる)」と定められています。
坊さんの罪については、「律(りつ)」(刑法)から流刑の一つである「身自ら(みみずから)嫁娶(かしゅ)し」(当人たちの意志で結婚する)に当てはまるかとも想像したりしています。
物語部分は、常体(だ、である)で表記しました。日常の語り口や、方言を入れたりなどして読んでいただけたらとの願いからです。
「底無し沼だから気をつけろ」と、注意されて遊びに行ったころの思い出を持つ人が、現在もたくさんいます。「いもりがいっぱいいた」とも話しています。
幸せには生きられなかった若い二人の「いのち」に、限りなくあわれを感じている村人の心を、いもりの悲しみに託して、ずっと語り継いできているのでしょうか。






