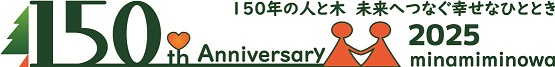本文
初歩からのみなみみのわ学(令和5年度)
広報紙「村報みなみみのわ」に連載中
人口(2)(村報2023.4掲載)
本村は、全国183村のうち、6番目に人口が多く、県内35村のうち最も人口が多い村です(※1)。ちなみに、全国で人口が最も多い村は沖縄県中頭郡読谷村の41,793人で、最も少ない村は東京都青ヶ島村の170人です。また、本村の平均年齢は43.8歳で、全国の村の中で9番目に若く、県内の市町村の中では最も若い村です。(※2)。
※1 令和4年1月現在住民基本台帳人口(総務省)
※2 令和2年国勢調査
人口(3)(村報2023.5掲載)
人口の増減には、「自然増減」と「社会増減」があります。自然増減は、そこで生まれた人数からそこで亡くなった人数を差し引いた数です。村は、統計上で確認できる限りでは、毎年自然増が続いており、近年では、県内で唯一の自然増自治体となることが多くありました。しかし、令和3年に初めてマイナス1人となり、この年、県内の自然増自治体はなくなりました。(社会増減については次回。)
人口(4)(村報2023.6掲載)
前月は「自然増減」でしたが、今月は「社会増減」のお話です。社会増減は、住民の転入数から転出数を差し引いた数です。村は、現在までほぼ社会増が続いていますが、社会減となった年が平成期に4回ありました。過去10年の平均社会増減数は、+97人です。転入元・転出先としては、どちらも伊那市が最も多く、次いで箕輪町となっています。
南箕輪小学校(村報2023.7掲載)
明治27年の天皇誕生日を祝うため学校で風船(熱気球)を上げた時、風船が校舎の草屋根にからみ、その火が燃え広がり校舎が燃え落ちてしまいました。火災後は仮校舎を建てましたが、新校舎が完成したのはその7年後となりました。明治28年福沢桃十校長先生は、学校が災害にあった時の財産の必要性を感じ、大変な苦労の末大芝に学校林を植樹したと言われています。
南部小学校(村報2023.8掲載)
それまで伊那地区の小中学校に通学していた神子柴原、南原、沢尻、地区の子どもたちが通学するため、平成8年4月に開校しました。中央アルプスの山並みが背景にある景色のよい場所にあり、全校児童が一緒に給食が食べられるランチルームを設置しました。(現在は児童数が増加し1、2年生のみ利用)他には、児童だけでなく地域の誰もが利用できる学校図書館があるのが特徴です。
南箕輪中学校(村報2023.9掲載)
昭和22年4月に開校した南箕輪中学校は、全校生徒で行う「経ヶ岳強歩大会」や「落穂拾い」など特色ある行事を伝統的に行っています。そして、大芝にある学校林では、明治以来生徒たちが毎年枝打ち作業や植林に取り組んでいます。また、南部小学校の学区の生徒を対象とした登下校時の無料スクールバスでの送迎は、上伊那の市町村では他にない珍しい取り組みです。
委託児童(村報2023.10掲載)
明治初期から神子柴原、南原、沢尻地区の子どもたちは、伊那市の西箕輪小中学校や伊那小中学校に通っていました。伊那市に児童の教育を委託していたため、このことを「委託児童」と呼んでいました。子ども達が村の小中学校で学ぶことを望む多くの方の尽力によって南部小学校が創立された後、伊那地域の中学校に在学していた中学生が卒業するタイミングに合わせ、平成11年3月に委託児童はすべて終了しました。
上伊那農業高校(村報2023.11掲載)
明治28年8月に当時の地域住民の要望から、郡立の農学校として伊那市伊那部(現在の伊那市狐島)の民家を借りて開校しました。その後、県立の学校となり何度かの移転を経て、昭和46年に現在の場所へ新校舎を建設しました。毎日生徒が通る「赤門」は、1922年にイギリス製レンガで造られた貴重な門で、旧校地から現校地に移設されたものです。昔の面影を残しながら今も生徒達を見守ってくれています。

信州大学農学部(村報2023.12掲載)
昭和20年2月、長野県農林専門学校として設立され、昭和24年5月の学制改革の際、信州大学に包括され発足しました。日本一標高が高い国立大学(標高約770m)として、豊かな自然環境に位置しています。
また、大学には生産品の直売所があり、季節ごとの野菜、果物や花、ワインやジャムなどの加工品を買うことができ、置いてある物は農学部の学生が作っただけあって品質も味も最高です。

役場庁舎(村報2024.1掲載)
現在の建物は昭和56年に完成しました。それ以前の庁舎は昭和8年から50年近く現在の上伊那農協南箕輪支所の場所にありました。
昭和8年当時の職員数は15人程度でしたが、人口増加、行政需要の増大や行政事務量の増加などに伴い現在では、166人となっています。また、令和6年度は大きな機構改革を行い、「子ども」や「福祉」に関わる窓口の一本化をするなど、住民サービスの向上のための取組みを続けています。

大芝高原(村報2024.2掲載)
村有林として育成されていた大芝原ですが、山林経営の不振による
財政基盤弱体化の改善、村民の憩いの場開設、中央道の開通などの複合的な理由から観光開発に踏み切ることになりました。スポーツ公園としての整備が始まり、昭和47年から野球場、陸上競技場、アーチェリー場、プール、テニスコートなどが整備されました。かつてのアーチェリー場は、昭和53年の国体記念全国都道府県対抗アーチェリー競技会の会場にもなりました。

大芝高原のスポーツ施設(村報2024.3掲載)
昭和50年代、陸上競技場は冬期間スケート場となっていました。
12月になると大泉川から水を引き、お正月頃には氷の厚さはなんと20センチにも。スケート場のオープン初日は、大人から子どもまで1日に延べ600人ほどがスケートを楽しんだそうです。また、昼間だけでなく夜間は照明設備を使い、「ナイトスケート」まで行われていました。当時から1年を通して「スポーツ公園」として賑わっていたようです。