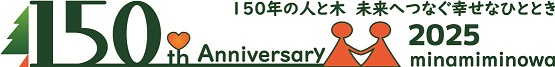本文
初歩からのみなみみのわ学(令和4年度)
広報紙「村報みなみみのわ」に連載中
村の誕生(村報2022.7掲載)
明治8年、久保村・大泉村・北殿村・南殿村・田畑村・神子柴村の6村が合併し、箕輪郷の南に位置することから、「南箕輪村」と命名しました。当時、塩ノ井と沢尻は久保村に属していましたが、明治22年に区制が施行され8区となりました。昭和21年には、戦後の開拓により北原・大芝・南原の3区が加わり、昭和50年に住宅団地造成により中込区が加わり、現在の12区となりました。
歴史上では、明治8年は、日本がロシアと樺太・千島交換条約を結んだ年です。村の歴史の長さを感じます。
村章(村報2022.8掲載)
市町村には、その市町村の紋章である「市町村章」があります。南箕輪村の村章は、「ミナミミノワ」を図案化したもので、約半世紀前の昭和49(1974)年に制定されました。左右の「ミ」は村の将来に向かって発展する姿と調和のある自然の美を、「ナ」は豊かな実りを、「ワ」は村民の和と協調を表し、全体で、平和で豊かな未来に向かって飛躍的に発展する姿を象徴しています。皆さんが目にすることは少ないと思いますが、役場庁舎の正面には、村章が描かれた「村旗」が掲げられています。

シンボルマーク(村報2022.9掲載)
前月号で村章を紹介しましたが、「それじゃあ、三角マークのあれは何?」と思った方がいるかもしれません。村の窓付封筒やwebサイト、役場の車両などで使われているこのマークは、村をイメージした「シンボルマーク」で、平成6年に制作されました。村章とシンボルマークの違いは、企業における社章とロゴマークの違いと同様に考えてもらえば分かりやすいでしょうか。三角部分は中央アルプス・南アルプスを、下部の2本の線は天竜川と中央アルプスから流れ出る清流を表現しています。

村の木・村の花(村報2022.10掲載)
都道府県、市町村などでは、郷土を代表する木・花・鳥などを選び定めています。本村の村の木は「赤松」、村の花は「菊」です。昭和50(1975)年11月23日に、村誕生100周年記念式典で制定されました。赤松は「天に向かい伸びる姿が、明るい南箕輪の未来を象徴しています。」、菊は「私たちの村、南箕輪村も、この菊のようにさりげなく可憐でありたいとの願いをこめて制定されました。」と、それぞれに当時の想いが込められています。
南箕輪村民の歌(村報2022.11掲載)
夕方のミュージックチャイムでおなじみの「南箕輪村民の歌」は、昭和36(1961)年に制定されました。作詞は、教員を勤めながら児童文学者として活躍し、日本児童文学「新人賞」「特別賞」などを受賞した加藤明治(かとうめいじ)さん(塩ノ井)です。加藤さんは、かつて村南部の中学生が通っていた伊那中学校の校歌も作詞しました。また、作曲は、南箕輪中学校の音楽教諭だった河西(かさい)(旧姓:遠藤(えんどう))温子(あつこ)さんです。その後、平成28(2016)年には、元音楽教諭の唐澤史比古(からさわふみひこ)さん(箕輪町在住)により合唱曲として編曲され、平成29年2月18日の村の日記念イベントで披露されました。
村の面積(村報2022.12掲載)
村の面積は、40.99平方キロメートルです。このうち約半分の21.7平方キロメートルは、伊那市西箕輪の西に位置する飛地で、人の住んでいない山林です。本体部分は19.2平方キロメートルで、このうち宅地(店舗・社屋などを含む)が3.9平方キロメートル、田・畑が9.1平方キロメートル、山林が2.8平方キロメートルです。本体部分は、東京都の港区(20.3平方キロメートル)と新宿区(18.2平方キロメートル)の中間くらいの面積で、コンパクトにまとまっている上にほぼ平地であるため、効率よくインフラ整備ができ、村の健全財政の一因となっています。
飛地(村報2023.1掲載)
村の区域の約半分は「飛地(とびち)」です。飛地とは、自治体の区域の一部が完全に離れており、他の自治体を通らないと行くことができない区域のことで、村の飛地の場合は、本体部分との間に伊那市西箕輪を挟んでいます。約150年前、6つの村が合併して「南箕輪村」となりました。合併前のそれぞれの村で、村人が薪や家畜の飼料などを採取していた共有地(「入会地(いりあいち)」という)だったところが本体部分に接していなかったため、飛地となり現在に至っています。飛地は主に森林地帯で、人は住んでいません。
まっくん(村報2023.2掲載)
まっくんは、平成6(1994)年に大芝高原のキャラクターとして生まれました。平成17(2005)年に村のキャラクターに昇格し、翌年デザインを一新してかわいらしく生まれ変わりました。平成23(2011)年には、ゆるキャラ🄬グランプリで最下位となり、「日本一人気のないキャラクター」として有名になりました。
旧まっくん

新まっくん

人口(1)(村報2023.3掲載)
南箕輪村が誕生した明治8(1875)年の人口は、2,333人でした。誕生100周年を迎えた昭和50(1975)年の人口は7,664人で、10年後の昭和60(1985)年には人口10,000人を達成しました。その後、日本は人口減少時代を迎えますが、村の人口は増え続け、令和4(2022)年10月には、人口16,000人を突破しました。この年、県内の77市町村中、前年より人口が増えたのは村を含め7町村で、上伊那郡内では村だけでした。